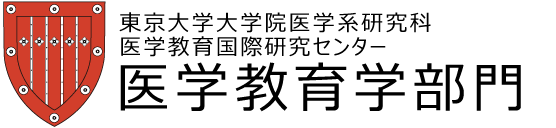現場に届けたい、もっと自由な学びを
interview #03/ 2025年4月10日
~医療教育におけるVRの挑戦をお伺いしました~
学歴
- 2007年 東京大学医学部医学科卒業
- 2022年 マーストリヒト大学 医学教育学修士課程修了
- 2023年~東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻 博士課程
職歴
- 2007年 公立昭和病院 初期臨床研修医
- 2009年 公立昭和病院 小児科 専攻医
- 2012年 国立成育医療研究センター 新生児科 フェロー
- 2014年 国立成育医療研究センター 新生児科 医員 (23年からは非常勤)
大学院に進学しようと思った理由を教えてください

日本の新生児医療は、世界でもトップレベルと評価されています。これは、私たちの諸先輩方が多大な努力と情熱を注いできた成果です。
医師や看護師、その他の専門職の方々が、文字通り命と時間を削ってNICUに貼り付き、きめ細やかな医療を提供してきたからこそ、現在の水準が築かれました。
しかし近年、医療システムの構造的な変化により、若手医療者が十分な臨床経験を積み、スキルアップすることが難しくなってきています。
限られた現場経験の中でいかに効率よく学ぶか、また、働き方改革で生まれた空き時間を活かして、どのようにOff-the-job trainingを行うかが、これからの重要な課題です。
これは新生児医療に限らず、すべての医療分野に共通する課題だと感じています。
こうした背景から、医療者教育の理論と実践への関心が高まり、まずは医学教育学修士課程で教育理論を広く学びました。
そして現在は、次のステップとして、新生児医療の現場に貢献できる学習手法の開発とその効果検証に取り組むため、博士課程に進学しています。
自身の研究の内容や目的について
バーチャルリアリティ(VR)技術を活用して、新生児蘇生法(NCPR)の自主訓練を行えるアプリを開発し、その学習効果を検証する研究に取り組んでいます。
従来、NCPRはマネキンを用いたシミュレーショントレーニングや、現場でのOn-the-job trainingで学ぶのが一般的でした。
シミュレーションは優れた学習方略の一つですが、指導者の存在やフィードバックの質に大きく依存し、高価なマネキンや専用資材も必要となるため、場所や時間の制約を受けやすいという課題があります。
一方、VRには触覚の再現という課題はあるものの、学習者が一人で好きなときに繰り返し訓練を行えることや、プログラムによる一定のフィードバックを提供できるという利点があります。
VRがシミュレーショントレーニングに取って代わるものではありませんが、両者が互いの弱点を補い合うことで、より柔軟で質の高い学習体験が実現できるのではないかと考えています。
博士課程の前半2年間は、臨床情報工学の小山博史教授のご指導のもと、簡素ながらもVRアプリの開発を行いました。後半は医学教育国際研究センターで江頭正人教授のご指導を受けながら、その学習効果の検証を進めていく予定です。将来的には、VRエンジニアと連携してアプリをさらに改良し、関連学会の協力を得ながら、NCPR学習プログラムの一環としてVRによる自主トレーニングが組み込まれることを目指しています。